ホーム >
一期一笑
2010/11/19
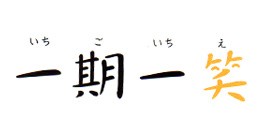
vol.13 拳のつながり
ある日の昼下がり、携帯電話に着信と留守電が入った。留守電を聞いてみると受験勉強のため休眠していた3人の中学生拳士の1人からだった。その拳士に電話をかけると、3人の中学生がそれぞれの志望校に合格したとの知らせであった。そして、今から私の家に来てくれるというのだ。わざわざ、報告に来てくれることに感謝しな…
法を問い学を修める
2010/10/01

vol.12 雷龍王の国ブータンに習う
ヒマラヤのふもとの小国、ブータンが世界中の耳目を集めたのは、1976年、スリランカのコロンボの会議で、ブータン国王が「国民総生産量」より「国民総幸福量」を目指すと発言したことに始まる。以来、ジグミ・シング・ワンチェク第4代雷龍王は、世界第1位と2位の人口を誇る大国に挟まれた小国が生き延びるための戦略…
あ・うん こぼればなし
2010/10/01

vol.12 子は親の背中を見て育つ
12号のこぼれ話は4ページの活動報告に掲載されていた本山の帰山行事について。記事にも書かれているように、今年の帰山の特徴に、保護者プログラムのスタートがありました。保護者プログラムとは、金剛禅の教えを実生活に生かす講義です。このプログラムを企画実行した宗務部の中山元宏次長にプログラムの意図を聞きまし…
一期一笑
2010/09/19
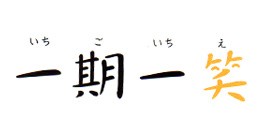
vol.12 合掌礼
いつだったか、拳士仲間でスナックに飲みに行ったときのことだ。店を出て合掌礼を交わしたところ、見送りにきた女の子たちに大笑いされてしまった。ふだん自覚しないが、外部の人の目には奇妙な習慣なのかもしれない。1995年のいわゆるオウム事件の後、ある大学の少林寺拳法部では、「駅や街頭では合掌礼をしなくてもよ…
一期一笑
2010/08/01
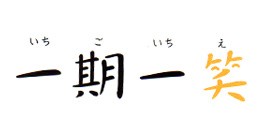
vol.11 コンカツ
コンビニと宅配便は、見事なまでに生活に浸透した事業である。便利さの追究が、小売業・流通業を根元から変革したのであろう。先日、コンビニに寄った。特別な目的など持たず、ふらりと入店、何となくボトル茶を庫より取り出し、レジに並んだ。大型チェーンの店、もちろんレジの向こう側のバイト君は、無機質に正統派マニュ…
法を問い学を修める
2010/08/01

vol.11 改革
昭和初期、誕生まもないラジオで「法句経」を講義して大きな反響を得た友松圓諦。「漢文の意味のわからないお経ではなく、わかるお経を伝えたい。わかる仏教、生活に生かせる仏教を」と問題を提起し、仏教ブームを巻き起こした友松。開祖も『少林寺拳法教範』を編纂するにあたり、友松著の『法句経講義』と『これからの寺院…
あ・うん こぼればなし
2010/08/01

vol.11 ダーマ
前10号から表紙の写真家が変わりました!これまでの金本孔俊氏のアラスカシリーズに続いて、「ダーマ」をテーマに作品を提供してくださるのは河合修氏です。今度の舞台は日本、身近にあるダーマを撮影してくださっています。1年の準備期間を経てのお披露目となりました。皆さん、純な心でダーマを感じてみてください。な…
一期一笑
2010/07/01
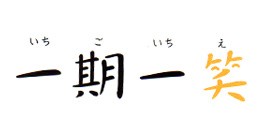
vol.10 武専修了
合掌。はじめまして。修了式当日、やっとの思いで兵庫武専の研究科4年の出席が7回となりました。残念ながら式では、証書は頂けませんでした(当たり前ですね!)。しかし、わが家へ帰ると、子供たちから「卒業おめでとう」と、かわいいデコレーションケーキのプレゼントを受けました。父子家庭の中、いろんな出来事をつく…
一期一笑
2010/06/01
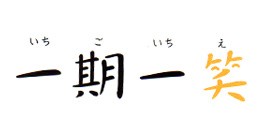
vol.09 今が一番動ける時
道を歩いていると、大きな荷物を抱え片足を引きずって駅に向かうご婦人を見かけました。お声をかけて途中までご一緒しながらお話していましたら、私もお会いしたことのある有名な義肢装具士の所に行かれるところでした。膝(ひざ)を悪くされていて、京都の知人の紹介で神戸から75歳とご高齢ながらお一人でいらしていまし…
法を問い学を修める
2010/06/01

vol.10 道院
「道院」という名称は、武道の道場と仏教の寺院とを合成した文字で、道院としたものだと、私は思っていた。『教範』をよく読んでいなかったのである。『教範』には中国の道院との違いが2ページにわたって記述されており、『50周年史』にも道院の満州総院で陳先生に小手巻返らしい技で開祖が投げ飛ばされたエピソードが紹…
あ・うん こぼればなし
2010/06/01

vol.10 内助の功
「人、人、人、すべては人の質にある」。道院も例外ではなく、そこに集まる人の質で大きな違いがでる。昨年のvol.6に続くシリーズ「人づくりの実例」では、今回、大日道院と境港道院を取材した。どちらにも共通しているのは、小さい子供から大人まで、自分の道院に誇りを持っていることだ。皆が自信にあふれ、道場内は…
一期一笑
2010/05/01
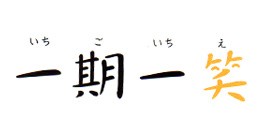
vol.08 出店が結ぶ人の縁
本山達磨祭に兵庫県教区として初めて参加しました。父が兵庫県教区役員をしていることから、地元の「姫路おでん」を作りました。前日から、姫路近隣の道場の保護者と一緒に大根や卵の殻をむき準備しました。ふだん、地元の「開祖デー」の出し物として取り組んでいるので経験はあったものの、5品で500人分のおでんは半端…

