ホーム > 金剛禅 コンテンツ
あ・うん こぼればなし
2013/10/01

vol.30 金剛禅の原点
今号は組織機構改革の意義と必要性を特集した。これからも変わらず誇り高く金剛禅運動を邁進していくための改革である。写真はまだひげを生やす前の開祖である。法衣に絡子、手に如意を持ち、道場の玄関に立つその姿に、金剛禅の原点を見る思いがする。敗戦の体験から「人、人、人、すべては人の質にある」と悟った開祖。開…
ふだん着の金剛禅
2013/10/01
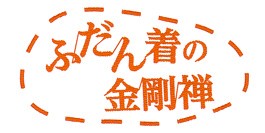
vol.31 明るい笑顔
私は同僚や上司からよく、「額にしわを寄せて、いつもしかめっ面をしている」と注意されていました。
最初は「そんなこと、どうでもいいじゃないか」と思っていました。しかしあるとき、開祖の語録に触れ、考えを改めました。「うれしい状態を自分でつくりなさい、だから妙な深刻な顔をするなよ。深刻な顔したって世の中変…
道
2013/10/01

vol.30 頂いた生命
1957(昭和32)年4月22日、奈良県桜井市に私は生まれた。母が私を身籠ったとき、体調を悪くし、母体の安全を考えて、出産を諦めるように医師から宣告をされた。しかし母は、私の命を最優先に考え、我が身のことなど考えず出産をした。出産後、母の体調は思わしくなく日常生活にも苦労をした。自分の命を惜しまず、…
志をつなぐ
2013/09/28
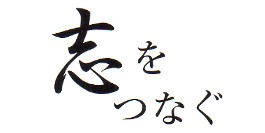
vol.30 濱田宏行 大導師正範士八段 199期生
「絶対に死ぬまでは負けたんでない。命さえあればどんなことがあってもいつかは立ち直れる」、この言葉を座右の銘としてきました。自宅が火事で全焼したときもこれを支えに乗り越えました。少林寺拳法で得た力をいかに社会に生かすのかが大切です。少林寺拳法の段位が通用するのは組織内だけです。井の中の蛙にならないよう…
道院長元気の素
2013/09/26
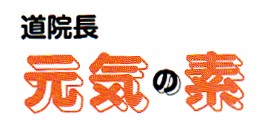
vol.30 讃岐府中道院 道院長 山下真司
道院長になろうと思ったきっかけは?学生時代は野球漬けの日々でした。高校卒業後、運動やスポーツは特にやっていなかったので20歳になり友人の誘いで軽い気持ちで坂出中央道院に入門しました。しかし、続ける中で金剛禅の思想、開祖の教えに少しずつ影響を受け、気付くとどっぷり少林寺拳法にはまっていました。いつかは…
一期一笑
2013/09/01
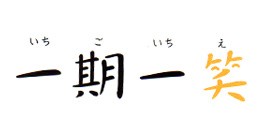
vol.30 子供に学んだ金剛禅
「開祖忌法要を行います」「礼」「直れ」「表白文、在天の祖師……」5月11日、栃木足利道院の開祖忌法要に道院顧問の鶴貝大祐氏(栃木県議会議員)が参列してくれた。氏は法要後の宗道臣デー活動・老人介護施設慰問にも参加された。鶴貝氏と栃木足利道院の関係は、14年前に氏のお子さんが小学1年生で入門したときに遡…
法を問い学を修める
2013/08/20

vol.29 幸福運動についての一考
数年前の7月、病院など通ったことのない妻が、数日前より体調を崩し、その朝、目の前で倒れました。救急車を手配し搬送されましたが、すぐに帰ってくるものと思っていました。しかし現実はそこから6か月の入院となりました。最初の40日は集中治療室で生死をさまよい、私もその間は、その前の待合ソファーで寝起きを共に…
あ・うん こぼればなし
2013/08/01

vol.29 開祖と夫人
今号は開祖夫人宗恵美子氏の顕彰特集を組みました。私が開祖夫人と初めてお話させていただいたのは、11年前、開祖の愛蔵品の撮影でご自宅におうかがいした時です。おっとりとした方だろうと勝手なイメージを膨らませていましたが、テキパキと采配鮮やかで気さくなお人柄でした。愛蔵品のレイアウトなども一緒に考えてくだ…
道
2013/08/01

vol.29 生きる
私にとって「道」とは、生まれてから死ぬまでの道のりのことであり、死ぬまでどう生きるかが道である。いつか自分が死ぬとき、この世に生まれてよかったと思える人生を歩んでいくこと。その道しるべが金剛禅の教えであり、生きる、生き抜くことが、金剛禅の教えの第一であると思う。私は双子として生まれ育ってきたが、やは…
志をつなぐ
2013/07/28
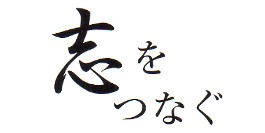
vol.29 甲斐哲夫 大導師正範士八段 177期生
開祖と初めてお会いしたときの、いちばん最初の言葉が「続けろよ」でした。そのときの温かな手の感触、今も忘れることができません。「北海道には鉄のカーテンが下りている」と言われ、地理的だけでなく精神的にも距離があった本山と北海道の間を縮めるべく尽力してきました。最初に言われた「続けろよ」を開祖の教えとして…
道院長元気の素
2013/07/26
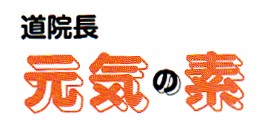
vol.29 淡路中部道院 道院長 新田福音
道院長になろうと思ったきっかけは?専門学校禅林学園には、金剛禅の教義を深めたいという思いで入学していました。その学生時代、道院長研修会に参加されていた先生から「あなたは卒業後、道院長になられるのですか?」と問われたことがきっかけでした。自分にもそういう道があるのだと思い立ち、その翌年11月、淡路中部…
一期一笑
2013/07/01
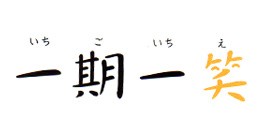
vol.29 きっかけは1本の電話
入門のきっかけは、1本の電話でした。当時、幼稚園年少の息子はとても泣き虫で、親としては、イジメられっ子にならないでほしいと心配しておりました。そこで、武道を身に付け、心も体も強い子に育ってほしいという願いから少林寺拳法の門を叩かせていただきました。右も左も分からない私は、東京センター(現・東京別院)…

